※本記事は、AIに焦点を当てたネタであり、将棋を知らなくてもお読みいただけます。
長年趣味にしてきた将棋について、ネタをまとめてKindle本を執筆して出版してみようというチャレンジをしてみたわけですが、その過程で生成AIを使っていて感じた内容を書いていきます。
(執筆した本はこちらです!kindle unlimited読み放題対象です📚)
気軽にパラパラと見て頂けますと非常に嬉しいです!
※↓広告ブロック対策で表示されない場合のリンクです
脱初心者!将棋の考え方: 読むだけで1級分上達する思考とコツ
本を書くうえで役立ったポイント
まず、本を書くにあたって生成AI(ChatGPT)が非常に役立ってくれたこととしては、校正や書面のレイアウトなどです。
最終的に本文の文字数は数万字を超え、一人でチェックするのは大変になってきていました。
誤字脱字や、文章の流れがおかしい所、説明が重複している所などを指摘してもらうのは非常に助かったところです。
また、イラストなどがない文章ばかりの本でしたので、少しでも読みやすくなればと、テキストを囲んだり下線を引くなどのデザインもしましたが、このデザイン例(CSS)もアイディアを貰えました。
内容面では結局、まだ人間の方が良いコンテンツを作れると感じた
しかし、コンテンツとして重要な、本のコンセプトや、伝えたい項目や文章は完全に自分で考えて書きました。
以下に書くような理由で、ここは現状のAIにおまかせしていては良いコンテンツができないと感じたのが正直な所です。
AIスゴイ系の記事は大量にあるので、この記事ではあえて、私が感じた、現状のAIでハウツー本を書くには、限界・弱点があるといった書いていこうと思っています。
※最新の生成AI動向について専門では無いので、適切なサービスやチューニングをすれば解決する問題もあるかもしれません。そのつもりでお願いします。
具体的な経験や感情に根差していない
当たり前ですが、AIには「人生経験」はありません。
そして、人間にアドバイスする時には、まず、話を聞こうと思ってもらわないといけません。
「自分も同じことで悩んだ」「どうやったらいいのかを深く考えた」など、実体験があるのと無いのでは、読者目線から見て、話しを聞こうという気持ちに差が出てくるはずです。
AIは文章の論理は筋が通っていて、言葉も丁寧ですが、やはり読んでいて楽しいかと言われると薄味になりがよなあ、と感じます。
ある意味で、人間の筆者の経験や、その人らしい考え方、のようなものが一種のエンタメ性となり、話のスパイスになるのではないかと思いました。
「どこで悩みやすいか」の勘所がずれやすい
こういった本では、「実際にどこでつまずくか、どういうアドバイスが欲しいのか」の勘所を知ることは、自分自身がその過程を経験したり、多くの人を見た経験が間違いなく大事だと思っています。
そういった部分は、デジタルデータとしてAIが十分に学習できておらず、そのような「勘所」がAIは理解できていないと感じます。
あえて伝えないような思考が難しいのではないか
私がこの本を書くときの方針として、今この瞬間に理解すべきことだけを書き、高度すぎる内容や、例外的なケースについて長々と書くことはあえて避けました。
厳密さや網羅性を重視して、稀にしか使わないような情報を詰め込んだり、難解にしてしまうと、本を通し読みするのが苦しくなり、理解度が下がると思ったためです。
9割がた使えるメッセージをブレずに伝えることが大事で、ノイズになりそうな事は省こうと思いつつ書いていました。
AIは「知っていることは漏れなく伝えたい」という傾向があり、対象の学習者のレベルに対して、何を伝えないか?と適切に取捨選択をしていくのは難しそうに思っています。
学習データが乏しいニッチな分野はイマイチ
科学などの学問であれば、情報が多いと思いますが、将棋というニッチ寄りのジャンルになると、自分でググる以上の役立つ情報は出てこないと感じますし、いい加減な情報も多い出てきやすいと思いました。
いつの日か、AIが将棋の棋譜データを解析して言語化できるような能力を持つようになれば、質量ともに大変な知見が得られると思いますが、現状では人間の上級者の方が、実戦的な知見を多く持っていると感じます。
とにかく無難な内容になりがちで、独自性がない
ウェブ情報を調査したうえで書かせたとしても、よくある情報の寄せ集めのものしか出来ていない、と感じました。
AIは既存の情報を要約したり、整理することは得意でしょう。
しかし、原理的に、誰も考えていなかった問題を考えたり、斬新な視点での思考を提供するのは苦手なはずです。
また、本質的ながら多数派の声にかき消されてしまっているような意見を拾うのも苦手だと思っています。
結局のところ現状では、この筆者だからこそだな、と思ってもらえるような記事はなかなか生まれないと思っています。
おわりに
AIの進歩はめざましいですし、将棋AIが近年ではプロを圧倒するほどの実力を身に着けたように、生成AIも将来的にはこれらの課題を乗り越えていくんだろうな、というのは個人的に思っている所ではあります。
また、冒頭に書いた通り、個人出版でも誤字脱字チェックなどの地道な作業や、デザインなどの専門性がない部分を一部任せられるようになったのは実際に大きなメリットだと思います。
伝えられるコンテンツがあれば、個人で未経験でも、割と手軽に本を作れるような環境になったのは素晴らしいことだと思っています。
しかし、現時点では決して、万能な存在ではないし、文章コンテンツで人間が上回ることはできるな、と感じているのが現状ですね。
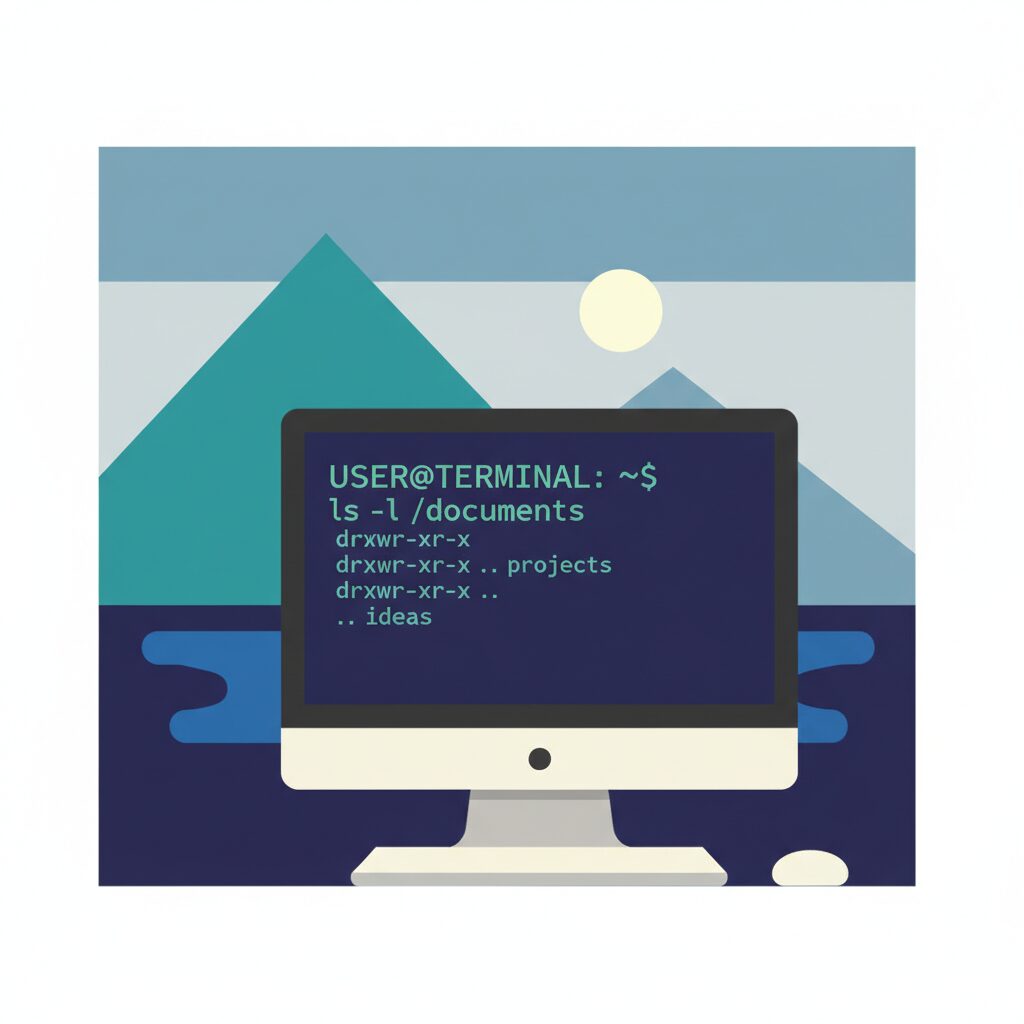
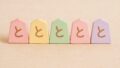

コメント