趣味としての指し将棋、参入ハードルが高くないか?
指し将棋は「勝てるようになって初めて楽しめる」趣味だと思います。
他の趣味と比較すると、楽しさの入り口に到達するまでのハードルが高い、ある意味「厳しい趣味」です。
少しでも棋力に差がある相手と対局すると、「何が起こったかわからない」うちに一方的に負けてしまいます。自分の駒が次々と取られ、それが相手の戦力となって盤面が絶望的な状況になっていく──これは他の多くのボードゲームと比べても、精神的にこたえる負け方ではないでしょうか。
しかも、将棋は運の要素がゼロです。実力差が非常にシビアに結果へ反映されるため、何度対戦しても「惜しかった」ということがなく、完敗し続けてしまいます。
他の趣味は「下手でも楽しい」
自分で打ち込むような、上手い下手があるような他の趣味と比べてどうでしょうか?
- カラオケなら音程がズレても、気持ちよく歌えれば楽しい。
- スポーツなら、下手でも体を動かすだけで爽快感がある。
- 創作や物作り系なら、自分の愛着のこもった作品が残ります。
将棋と近い頭脳ゲームの世界でも、
- ボードゲームなどは、かわいらしいデザインや世界観、実力とは別の楽しさの要素が用意されているものが多いです。
- 運が絡むゲームであれば、初心者でもビギナーズラックがありえます。
- 麻雀などは、高い手をアガれたり、役満が出たりと、初心者でも楽しい盛り上がりのある瞬間が時々訪れてくれます。
これらと比べると、将棋は「勝てるようになって、ようやく楽しさが見えてくる」というハードな性質が際立っています。
先細りへの危惧と、将棋への想い
娯楽に溢れる現代において、こうした「厳しい趣味」のコミュニティは先細りしてしまうのではないかと危惧しています。
即座に勝て、報酬ももらえるように設計されているソーシャルゲームが溢れる中で、勝てるまでに一定の努力が必要な将棋は相当なハードルの高さです。
「こんなに何度も負かされて辛い思いをするんだったら、やらなくていいか」と諦められても自然なことだと思います。
私自身、幼い頃から将棋に親しみ、父や祖父との大切な思い出を作ることができました。だからこそ、将棋というすばらしい文化が衰退してしまうことには寂しさを感じます。
(一方で、私自身、子供の頃に父親に容赦なく6連敗させられて泣いた経験もありますが…w)
現状の課題として、初心者の「谷間」が深い
現状、ある程度のレベル(将棋ウォーズ2級程度以上)に達した人向けのコンテンツは、もはや無限と言えるほど充実しています。そのレベルになれば書籍も理解でき、プロの解説も楽しめ、自分なりに将棋の世界を歩んでいけるでしょう。
しかし、ルールを覚えたレベルから3級程度までの層が最も困難な状況にあると感じています。
この段階は、まだ思うように勝てないし、どのように将棋の局面を考えたらいいのか、指し手の意味がわからないなどの苦労も多いはずです。
楽しさを感じる前に心が折れてしまうケースも多いのではないでしょうか。
※ここでひとつ宣伝させてください※
この「谷間」を越えてもらうために、なるべく凝縮した形で将棋の考え方を伝え、できるだけ早く実力をつけて「勝てる楽しさ」に辿り着いてもらえるような入門書を書きました!
📚 Kindle Unlimited会員の方は無料でお読み頂けます!
※↓広告ブロック対策で表示されない場合のリンクです
脱初心者!将棋の考え方: 読むだけで1級分上達する思考とコツ
解決案①:ペア将棋で“勝ち体験”を共有する
上級者が初心者に教える時の一つの方法として、ペア将棋が良いのではないかと思っています。
たとえば、ぴよ将棋のような丁度よい強さのAIと、1手ずつ交代で指し、その中で上級者が:
- 指し手の狙いを口に出して説明する
- 囲いや駒組みの実戦例を見せていく
- 実戦の中で自然に将棋の考え方を伝える
こんなやりとりをしながら、上級者を敵ではなく、味方にして、一緒に勝ちを目指すのです。
初心者にとって、これは「ただ負けまでの時間を過ごす」だけの将棋ではなく、勝てる体験を共有する機会になります。
従来では、駒落ち対局が指導の定番でしたが、教わる側にとってはプレッシャーやハンデへの抵抗感があります。また、駒が大幅に減った状態では平手将棋との違いが大きく、実戦的な経験として活かしにくい面もあると思っています。
ペア将棋は「一緒に勝とう!」と並んで盤に向かえる、やさしい形だと思います。
解決案②:「拡張ルール」で将棋をもっと自由でキャッチーに
もうひとつのアプローチとして、キャッチーで楽しみやすい「拡張ルール」で一緒に遊ぶという可能性もあるのではないでしょうか。
ボードゲームの世界では、人気の出たゲームに対して、アレンジや追加要素でゲームバランスを調整した「拡張版」を出すのはよくある話です。
麻雀などでも、より派手になるよう歴史的に定番のルールが変わっていますし、各地方で受け入れられているローカルルールも非常に多彩です。
こうしたものが将棋でもメジャーな流れとしてあってもいいのではないかと思っています。
本将棋がこれほど夢中になる人の多いゲームなので、アレンジの仕方も色々とありそうです。
例えば、VTuberがよりコンパクトな将棋である5五将棋を配信枠の中でやるのを時々見かけます。これも将棋がコンパクトな形になり、配信時間の中で手を付けやすくなったからだと思います。
また、鈴木大介先生のYouTubeチャンネルで、変則将棋の一つであるインベーダー将棋をされている動画がありましたが、プロがこうした動画で変則将棋を指すのはとても面白い試みだと思いました。(爆笑させてもらった、お気に入りの動画です!)
※その動画はこちら👉
「本将棋」にこだわらず、ルールや構造を柔軟に変えることで、将棋との”距離”を縮めてもらうこと、駒を触ってもらって楽しい経験をしてもらうこと、が大事なのではないかと思うのです。
「自力で本将棋で勝てなくても楽しい」と思われてほしい
とにかく、将棋が「負けてばかりで辛いゲーム」ではなく、「一緒に指すことで楽しい」「素晴らしい交流ツールになる」と感じてもらいやすくなることが大切だと思っています。そのためには、現状から、もっと楽しさの間口を広げていく工夫が必要なのではないか、と個人的に思っているというお話でした。
微力ながら、将棋に楽しませてもらった者として、そんな未来の実現に少しでも貢献できればいいな、と思っています!



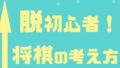
コメント